ITERの目標と経緯
ITERの目標

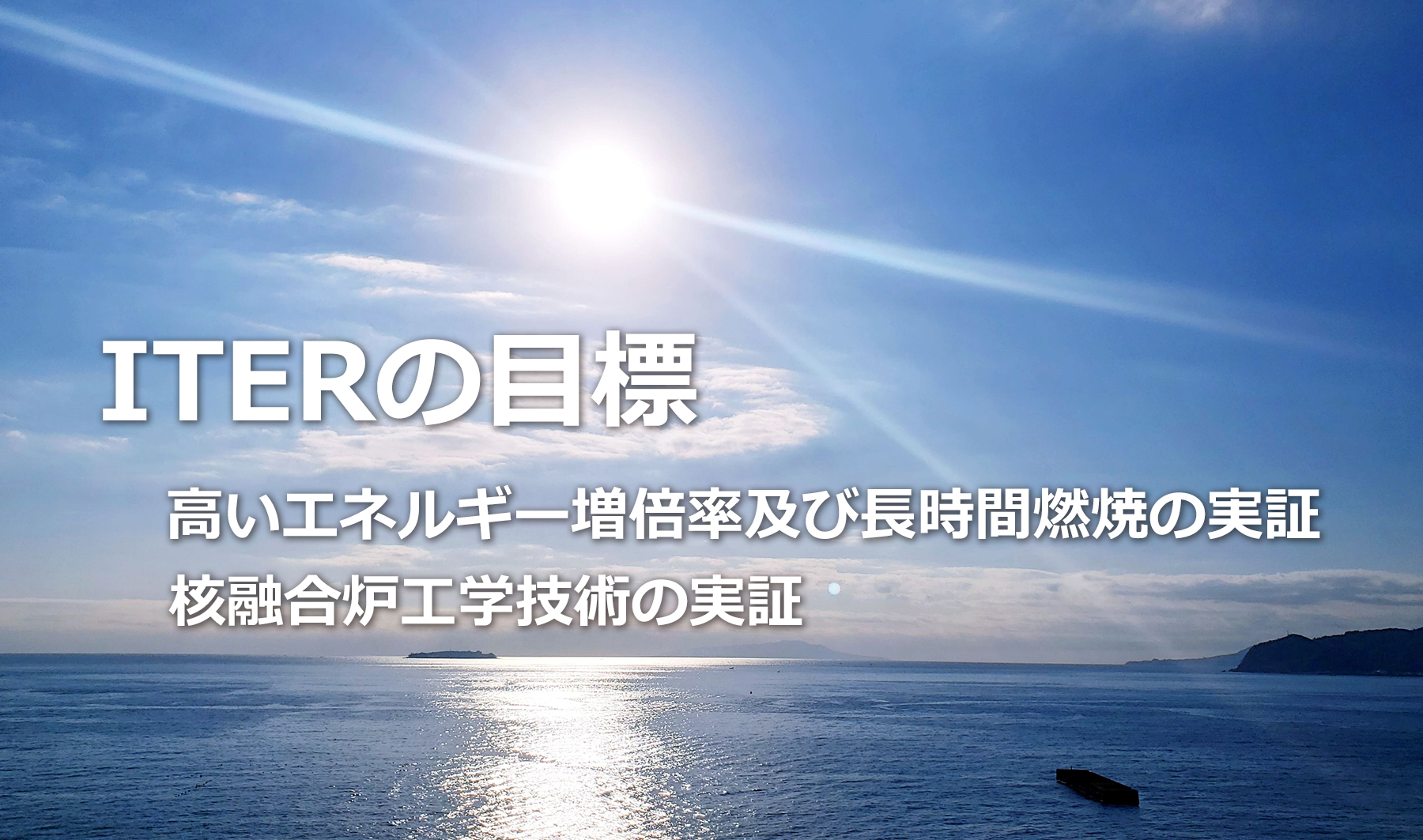
核融合は星や太陽のエネルギー源であり、我々はこれを地上に実現しようとしています。 ITERの目標は核融合炉と同じレベルの温度、密度などのプラズマを実現することです。 すなわち、三重水素、(トリチウム)と重水素という実燃料を用いて、大出力長時間の燃焼を行うことです。それには超伝導コイルなどいろいろな新しい工学技術が必要です。それに、 もちろん、核融合の安全性を実証するものでなければならないと考えています。
下の動画では、ITERとは何か、なぜITERを建設するのか?新しいエネルギー源「核融合」を実現するために必要なものとは?簡単に3分で紹介しています。
【日本語版】3分で分かるITER)
ITERの経緯

「ITER(イーター)」は、平和目的のための核融合エネルギーが科学技術的に成立することを実証する為に、人類初の核融合実験炉を実現しようとする超大型国際プロジェクトです。
1985年に当時のソ連にゴルバチェフが出てきて民主化が始まったのですが、そのときの米ソ首脳会談で核融合の国際協力が話し合われたことが、ITER計画のきっかけです。
ITERは米ソのほか日本、EUの4極の国際協力として、1988年から1990年までは概念設計活動が行われました。その後、ソ連からロシアへの移行を経て、1992年から9年間に渡って工学設計活動(EDA)を実施しました。
1999年には、米国が工学設計活動の延長に際しITER計画から抜けることとなりましたが、日本、EU、ロシアの3極により、2001年7月に最終設計報告書をまとめて設計活動を完遂しました。EDAの終了後、再参加した米国に、新たに参加した韓国と中国を加えて、建設サイトについての政府間協議が行われ、2005年にサン・ポール・レ・デュランス(仏)に決まりました。2005年末にインドがさらに参加しましたので、世界人口の半分以上を占める国々が参加する国際共同事業になりました。
政府間協議と並行して、EDAの成果を建設活動に円滑に繋げるために、ITER移行措置の活動が那珂(日本)とガルヒン(独)の作業サイトで実施されています。しかし、これらのサイトは2006年末に閉鎖され、作業サイトはサン・ポール・レ・デュランスに一本化されました。このサン・ポール・レ・デュランスの作業サイトに、2007年10月にITERの建設と運転を主導するITER国際核融合エネルギー機構(以下、ITER機構)が設置されました。
以下にこれまでの経緯についてまとめました。
| 1985年 | 米ソ首脳会議で核融合の国際共同開発に合意したのが発端となり、日欧にも呼びかけてITER計画が発足した。 |
|---|---|
| 1988-1990年 | 概念設計活動(CDA)がガルヒンク(独)で、日欧露米の4極により実施された。 |
| 1992-1998年 | 工学設計活動(EDA)がサンディエゴ(米)、那珂(日)、ガルヒンク(独)で4極により実施された。 |
| 1998年 | 日本提案によるコスト低減に向けた設計の大転換があった。 |
| 1998-2001年 | 米ソ首脳会議で核融合の国際共同開発に合意したのが発端となり、日欧にも呼びかけてITER計画が発足した。 |
| 2001年 | 最終設計書が完成して工学設計活動が終了し、設計に必要な技術的準備が完了した。 ・公式政府間協議によるサイト選定作業が開始し、2005年に、日欧露米韓中の6極による政府間協議において、建設サイトがサン・ポール・レ・デュランス(仏)に決定した。 ・EDAの終了後、建設が開始するまでの間、EDAで得られた成果を維持しつつ設計を深めるために、調整技術活動とITER移行措置活動(ITA)が那珂とガルヒンクに国際チーム作業サイトを設置して進められてきた。 |
| 2005年末 | サン・ポール・レ・デュランスに作業サイトが開設され、2007年の初めに、作業サイトはサン・ポール・レ・デュランスに一本化された。 |
| 2007年10月 | ITER機構が発足が発足して建設段階が開始され、ITAは終了した。 |
*「International Thermonuclear Experimental Reactor (国際熱核融合実験炉)」が「ITER」の語源ですが、 現在は「ITER」(イーターと読みます)が正式名称です。
*ITER建設地については、ITER機構の表記に合わせ、これまでの"カダラッシュ"(地元の呼称) から"サン・ポール・レ・デュランス"(行政住所) へ変更しました。
 量子科学技術研究開発機構
量子科学技術研究開発機構 ITER計画
ITER計画  エクス・アン・プロヴァンス観光/生活マップ
エクス・アン・プロヴァンス観光/生活マップ
